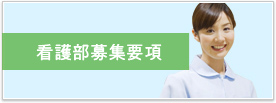病院で死ぬということ
もう十年以上も前になるのでしょうか、山崎章郎氏の書物がベストセラーになり、さらに映画化もされました。それから、ターミナルケア、ホスピスなど、どちらかといえばそれまでタブー視されていた「人の死に方」が話題に上る機会が増え、リビングウィル、尊厳死、延命処置といった言葉が日常的に患者さんや家 族との会話の中にも登場するようになってきました。
さて、在宅医療の普及で、畳の上での臨終が美化されているように思われますが、現実では死亡の場所はどうなっているのでしょうか。厚生省の統計による と、昭和26年には病院死亡9.1%に対して、在宅死(老人ホームを含む)82.5%と圧倒的に畳の上が死亡場所の主流でした。ところが昭和50年に 41.8%対47.7%とほぼ同率となってから病院死亡がどんどん増加、この書物が発行された平成2年71.6%対21.7%と7割以上を病院が獲得して 以後、平成11年からは病院77~78%、在宅 19~15%とほぼ横ばい、しかし病院の微増で推移しています。病院が臨終の場所として大きな需要がある ということなのです。
畳の上で死ぬためには、本人はさておき、見守る家族の勇気と主治医の努力が不可欠です。老衰のため摂食低下、在宅で(老人ホームでさえ)老衰死まで見守 る我慢ができず入院、延命処置を望まない家族に「輸液も延命処置です」ときっぱり言うことができるでしょうか。しかしその時の輸液で元気回復するかもしれ ない、輸液を開始したら中止できず在院日数が長期化する。頻回に誤嚥肺炎で入院、一回ごとに肺炎の治療、何度目かの入院病院が死亡の場所になる。呼吸状態 が悪いのでと、土曜日夜の入院依頼は、ホームドクターのプライベートタイムを担保するものでした。こんな入院も当初は急性期にちがいない。しかし急性期と して多くの検査、処置、治療は必要なく(すればできるが)、本人の希望通りの(?)終末期医療になるならよし、主治医を悩ませながらいつのまにか慢性期療 養に移行していることも多いのです。「老衰」とどの時点で診断するのか診断基準はありません。
介護保険の普及とともに、在宅サービスの多様化、また医療においては在宅訪問診療、在宅末期医療総合診療料のほか、在宅における悪性腫瘍、TPN、人工 呼吸など医療の進歩を在宅へと拡げ、これらの指導管理料など細かく複雑に設定されています。政策主導での病院医療から在宅医療へと誘導された上に医療費か ら介護給付へと支払い源を移行しての縮小。療養病床までも全廃されようとしている環境で、本当に、畳の上で死ぬということが本人も家族もどちらも幸せな事 なのでしょうか。78%以上の死亡が病院であるという現実。、急性期と末期医療の舵取りの方向を誤ってはいけないと思います。
兵庫県私立病院協会会報より